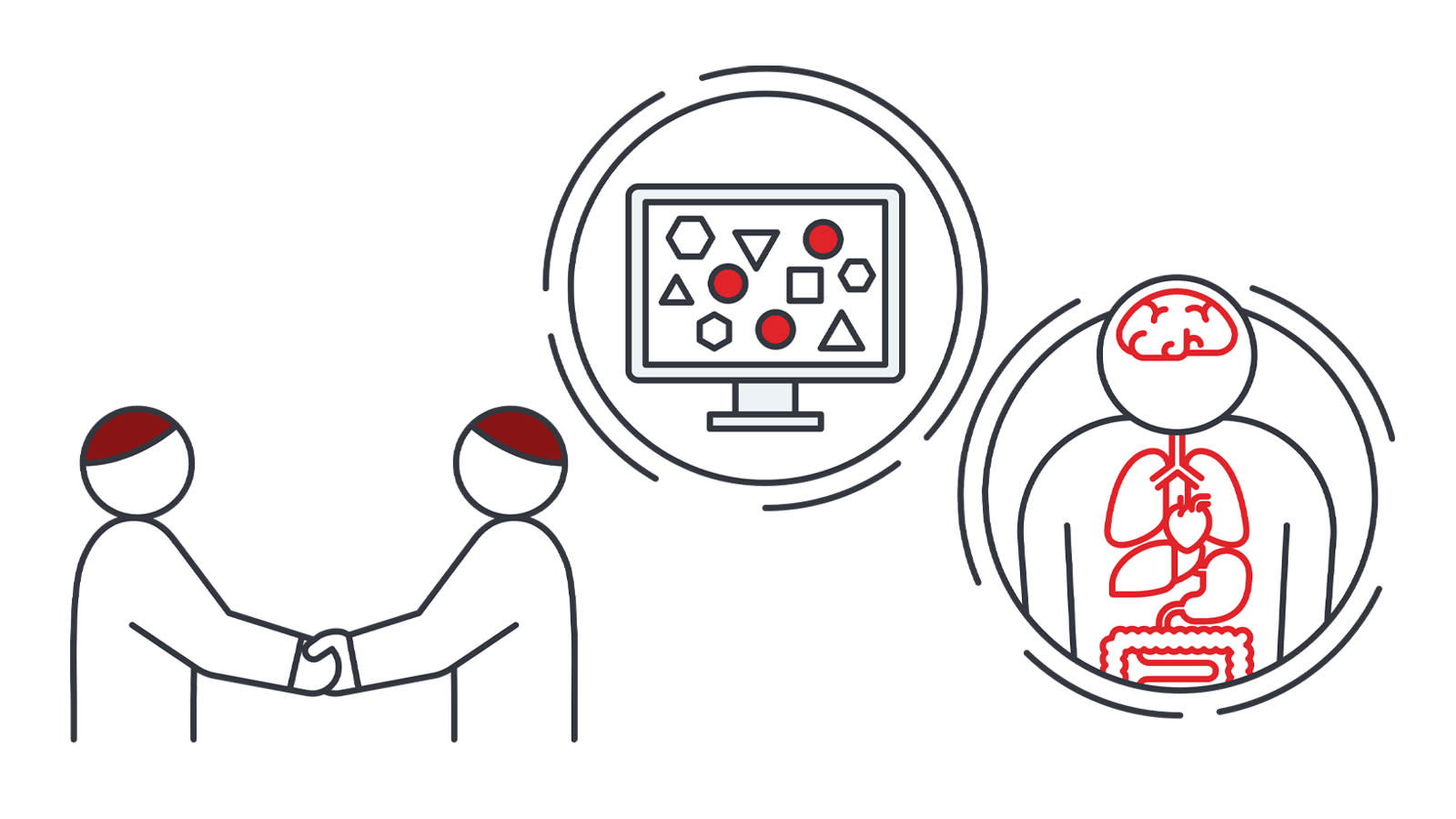共創を生み出す「希少疾患白書」ってナンダ? | 武田薬品
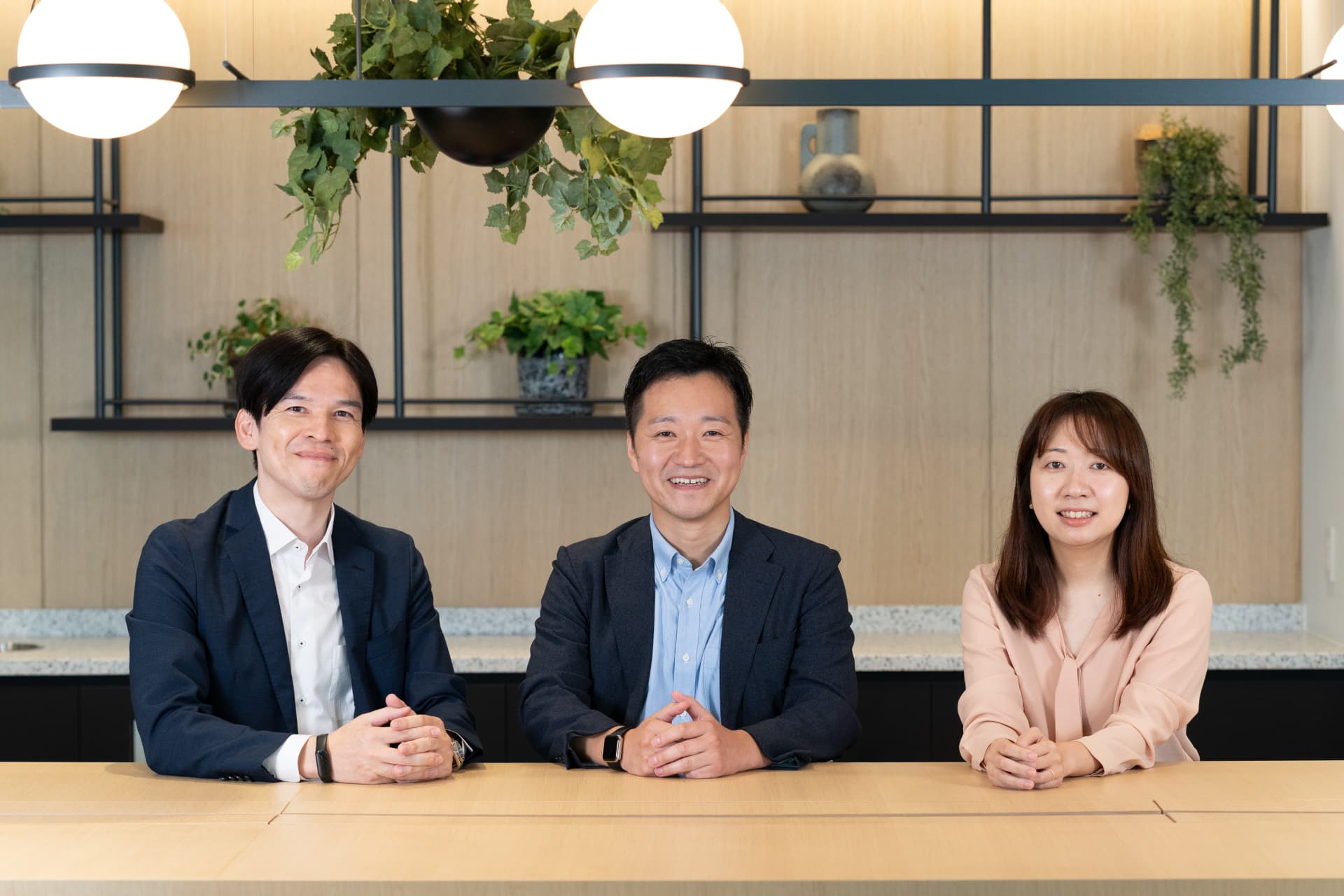
共創を生み出す「希少疾患白書」ってナンダ?
業界先駆けの白書アップデートで建設的な議論を促進
タケダは2025年8月に、「日本における希少疾患の課題」(以下「希少疾患白書」)を約5年ぶりに改訂しました。本白書は業界に先駆けて創刊されたもので、希少疾患患者さんを取り巻く環境や課題を分析・共有するほか、建設的な議論を促すために提言をまとめています。希少疾患とは、患者数が極めて少ない疾患を指し、日本では患者数が5万人未満と定義されています。希少さゆえに、疾患への理解が社会の各層で十分ではなく、患者さんの声が研究や治療法開発、ひいては医療政策に十分反映されにくいという課題があります。
今回は、希少疾患白書の改訂をリードした医療政策担当の林さんと、患者さん支援の中心的役割を果たした井上さん、そして希少疾患白書創刊に関わり、現在は希少疾患領域のグローバル政策をリードする飯村さんに、お話を伺いました。
希少疾患白書誕生に込めた想い
― 希少疾患白書創刊の背景と約5年ぶりにアップデートした理由を教えてください。
【飯村】 私が希少疾患に携わることになったのは、タケダ スイスに勤めていた頃、希少疾患に関するワークショップに参加したことがきっかけでした。そこで患者さんの声を聞き、「確定診断まで5~7年かかる(希少疾患白書の初版当時)」という事実に衝撃を受けました。「診断にたどり着けない苦しみを、どうすれば解決できるのか?」という課題感を強く抱き、当時の仲間たちとともに動き始めました。一企業が希少疾患の白書を出した前例は日本になく、関係者と協力しながら試行錯誤を重ねたことを今でも鮮明に覚えています。

【林】 希少疾患にかける想いや希少疾患白書の目的は、初版から変わっていません。ただ、初版発刊から約5年が経ち、患者さんを取り巻く環境が変化してきました。そしてタケダも、重点領域として希少疾患への取り組みを続ける中で、課題をより明確に捉えられるようになりました。希少疾患の患者さんを支えるエコシステム構築を、ステークホルダーの皆さんと推進できるよう、今回のアップデートでは新たな知見を反映しています。

治療薬開発や治療費助成に対する環境変化
ー日本国内では具体的にどのような変化がありましたか?
【林】 初めて希少疾患白書を発刊した5年前と比べて、治療薬の開発や治療費助成の考え方がより柔軟になりました。具体的には、2023年10月に難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)の改正により、患者さん側での一時負担金の助成までに必要な時間が短縮されたり、助成開始タイミングの考え方が重症化時点からになったりしました。
また、厚生労働省をはじめとする行政機関の尽力により、海外の治験データを使って治療薬の承認申請が認められるケースも出始めています。希少疾患の治療薬は特に、海外で使える薬が日本では使えない「ドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス」の傾向が大きいとされていますが、特に「ドラッグ・ラグ」については着実に改善に向かいつつあります1)。
【井上】 患者さんの視点で考えると、情報のデジタル化が進み、希少疾患に関する情報へアクセスしやすくなりました。例えば、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所による「難病治験ウェブ」を通じて全国で実施されている難病や希少疾患関連の治験情報に簡単にアクセスできるようになりました。これまでも治験情報は公開されていたものの、難病や希少疾患に特化したものではなく、必要な情報にたどり着くのに時間がかかる場合もあるという声が、患者さんから挙がっていました。
また、希少疾患に関連するアプリの数も増えてきました。患者さんが自身の症状を記録・可視化するアプリを利用することで、医療従事者とのコミュニケーションがより円滑に行えます。さらに、インターネットやアプリを通じて、患者さんやご家族、医療関係者など多くの人が希少疾患の学びを深められる環境が整いつつあります。

―世界的な環境の変化を教えてください。
【飯村】 2025年5月の世界保健総会(WHOの最高意思決定機関)で「希少疾患をグローバルヘルスの優先課題と宣言する画期的な決議」2)が採択され、世界的に希少疾患が公衆衛生の優先事項として位置づけられました。これにより、各国で診断・治療体制の整備や国際的な研究協力が一層進むことが期待されます。これは、希少疾患分野にとって非常に大きな一歩です。
一方で、7,000種類以上あるとされる希少疾患のうち、治療薬がある疾患は世界でまだ5%にとどまっています3)。こうした現状を改善するためにも、希少疾患治療薬への研究費助成や開発期間短縮を後押しするような仕組みを、制度として確立するのを求める声が挙がっています。
希少疾患白書発刊後に広がる連携、深まる議論
― 希少疾患白書を発刊してから、どのような反響がありましたか?

【林】 希少疾患白書をきっかけに、業界全体で議論や取り組みが進みました。日本製薬工業協会(製薬協)では「難病・希少疾患タスクフォース」も新設され、希少疾患を取り巻く環境改善に向けて活発な議論が行われています。
【井上】 患者団体からは、勉強会で希少疾患白書を活用しているという声をいただきました。日本だけでなく海外の事例も紹介しているため、まだ日本では取り入れられていない取り組みを知るきっかけになっているそうです。それが、活動の意欲向上にもつながっているとのことです。
多方面からアプローチ
―希少疾患白書以外で、タケダはどういった取り組みを行っているのでしょうか?
【井上】 行政との意見交換、研究コンソーシアムへの参画、製薬協の難病・希少疾患タスクフォースのリードなど、私たちは多くの活動に参加し、リーダーシップを発揮しています。

私の所属する患者・疾患啓発チームのミッションは、患者さんの声を集め、企業活動に反映させること、診断が課題となっている疾患について早期診断に寄与することです。例えば、患者さん向けセミナーを開催して患者さんのお気持ちや日常生活の中での疾患マネジメントについて情報発信や、患者さんをサポートするアプリの開発、短腸症候群※の患者さんでも安心して食べられる料理のレシピ公開など、患者さんの支援につながるさまざまな取り組みを行っています。
※ 腸管を大量に切除したため、消化吸収機能が極端に低下した状態。―グローバルでの取り組みを教えてください。
【飯村】 タケダは、国際製薬団体連合会(IFPMA)やRare Diseases International(希少疾患領域の国際患者組織ネットワーク)など国際組織とも連携し、グローバルレベルで希少疾患に関する政策設計にも寄与しています。
もちろん本業の創薬でも、希少疾患患者さんへ貢献しようとしています。現在の開発パイプラインの半数以上※は希少疾患または患者人数が限られている疾患へのアンメット・ニーズに対応し、さらに拡充することを目指しています。例えば、希少な神経性疾患などの治療薬の開発を進めています。
※ 2024年12月時点
希少疾患の未来を拓く共創と日本の役割
―希少疾患へどのように貢献を続けるか、今後の取り組みや期待を聞かせてください。
【林】 希少疾患白書が活用されることで、患者さんの声が政策に反映されるようになることを願っています。現在の政策決定プロセスでは、ヒアリング対象は医師や製薬業界に限られることが多くあります。希少疾患白書がきっかけとなり相互理解の重要性がもっと認識されることで、患者さんも含めた関係するステークホルダーが政策決定プロセスにもっと関われる機会作りに貢献できればと思っています。
【井上】 希少疾患白書を通じて、「共創」の意識がより広がることを期待しています。希少疾患の中には、症状が出ていても正確な診断がされず、診断までに時間がかかるケースが少なくありません。そのため、患者さんに加えて医療従事者への認知拡大も重要です。ステークホルダーの皆さんと協働して、患者さんや医療従事者に対して適切な情報を確実にお届けできる体制を整えたいと考えています。
【飯村】 グローバルレベルで希少疾患に対する関心が高まる一方で、一部地域では医療環境の整備が課題となっています。日本がこれまで培ってきた知見や取り組みを広く共有し、各国と共創しながら、世界中の希少疾患患者さんに貢献できると考えています。

Profile

飯村 真也
グローバルパブリックアフェアーズ
グローバルパブリックポリシーリード
希少疾患やデジタルヘルスなどの国際的に重要な政策課題に対し、世界中の社内外ステークホルダーと連携し、グローバルな政策形成とアドボカシー活動をリード。

井上 智子
医療政策・ペイシェントアクセス統括部
患者・疾患啓発
ペイシェントアドボカシー担当として主に希少疾患の患者団体とのコミュニケーションや疾患啓発ウェブサイトの企画・運営、業界団体におけるPPI(Patient and Public Involvement)推進活動を担当。

林 勢祐
医療政策・ペイシェントアクセス統括部
産業政策部 政策企画
政策分析を通じた政策動向のフォーキャスト作成、業界団体での活動を通じた薬価制度改革の提言活動を行っている。
引用・参考文献
1) 厚生労働省. (2024, 2月9日). 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会について. 2) 世界保健機構. (2025). Seventy-eighth World Health Assembly – Daily update: 24 May 2025. 3) The Lancet Global Health (2024). The landscape for rare diseases in 2024. The Lancet. Global health, 12(3), e341. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00056-1